上越地方を旅していきます。
上越妙高駅

上杉謙信像がありました。

越後といえばやはり謙信が最大の英雄です。

第三セクターのえちごトキめき鉄道を利用。妙高はねうまラインで高田へと向かいます。


高田駅

1971年に高田市と直江津市が合併し、上越市となりました。雪国だけあって中央通りにはアーケードがひたすら続きます。

雁木通り

雪国の上越地方では、昔ながらの雁木も見られます。

雁木とは町屋の庇を長くして、下を通路とした通りのことです。

このあたりは大町という通りです。


高田公園

高田公園(城址公園)にやってきました。外堀の蓮はすごい。


高田城址公園は桜の名所で全国的に有名です。




高田城 三重櫓

平成5年に復元された櫓です。松平光長時代のものを参考にしているそうです。

高田城は江戸時代の最初期、初代藩主・松平忠輝(家康六男)の命によって築かれました。高田城は最初から天守閣は造られず、この三重櫓をもって代用していました。

忠輝はその粗暴さを家康から疎まれ、高田城築城から2年後に城地を没収され、配流を命じられました。

その理由は諸説あります。忠輝がキリスト教布教に寛容であったこと。ヨーロッパとの貿易に積極的だったこと。また忠輝の妻・五郎八姫の実父・伊達政宗の存在など。策士の政宗が、忠輝を焚きつけて将軍家に弓引く危険性を感じていたのかもしれません。

その後も別の松平一族が高田を治めました。なかでも家康次男・結城秀康の孫にあたる松平光長の藩政は長く、58年にも及びました。

極楽橋が見えてきました。

極楽橋は二の丸と本丸を区切る内堀にかかります。

極楽橋。明治時代になって陸軍13師団が入城した際に、堀は埋め立てられ陸続きとなりましたが、2002年に木橋として復元されました。

目に見えない部分では鉄筋コンクリートやPHCパイルなど、近代的工法で補強されています。


高田城本丸跡です。

ここには城主の御殿や多くの建物が存在していました。1908年に陸軍が入城した際、土塁は切り崩されましたが、基本的な原型は保存されています。

旧師団長官舎
陸軍第13師団の師団長官舎です。明治時代の貴重な和洋折衷建築の一つです。

長岡外史中将の像です。長岡中将がこの師団長官舎をつくるよう命じました。すごい髭の明治陸軍の名物男です。プロペラ髭と呼ばれていました。

日露戦争では旅順攻略に海岸砲の導入を具申したり、樺太作戦を具申したり、奇抜なアイディアで知られました。

また長岡はオーストリア=ハンガリー軍のレルヒ少佐をこの地に招き、スキー指導を要請。ここから高田は「日本スキー発祥の地」とされるようになりました。

1階は一部レストランに使われているようですが、それ以外の部屋は無料で見学自由。

二階です。

1991年までは陸上自衛隊高田駐屯地の幹部宿舎として使用されていました。


お馬出し公園です。お馬出しとは城郭の虎口(出入り口)に造られ、大手門を敵の侵入から守るための場所でした。この公園は周辺の住宅地より低いので、お馬出しの堀にあたる部分だったと考えられています。

五郎八姫の森です。初代藩主・松平忠輝の奥方にして、伊達政宗の娘の五郎八姫にちなんで、イロハ紅葉が植樹されています。五郎八と言えば沢口靖子ですね笑

ちょっと雨に降られましたが、まあ小降りでそこそこ快適に町巡りできた。







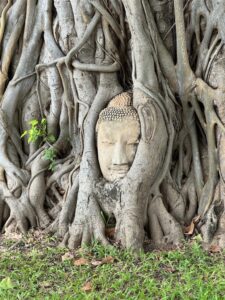




コメント