JR金谷駅
静岡県の島田市にやって来ました。JRの金谷駅です。

こちらは有名な大井川鉄道の駅です。


グッズで盛り上がってます。


SLで有名。今回は乗りませんが。

旧東海道石畳
金谷駅そばに案内があったので行ってみることにしました。

なかなかの風情です。

すべらず地蔵。しかしこの直後に転倒しました。

もともとは幕末に、牧之原の丸石を使って造成したもの。

維新後に失われたものを平成になって復元しました。

平成になってから復元された古の遺物は多い。




ふじの国茶の都ミュージアム
金谷まで来た本当の目的はお茶ミュージアムに行くことです。金谷駅からバスで移動しました。

着きました。

「ふじのくに茶の都ミュージアム」は、お茶の産業・歴史・文化を紹介する展示のほか、茶摘み・手もみ体験や、五感で感じる講座を充実させ、子どもから大人まで楽しくお茶について学べる機会を提供しています。

庭園が見えます。

天気が良ければ富士山が見えます。


茶の起源とも言われる雲南省の樹齢千年茶樹レプリカです。


英国にはアフタヌーンティーの文化が栄えます。

モンゴルのティーセットです。

湖心亭レプリカです。上海の茶館の復元です。


チベットではバターのようなものを入れて、お茶を飲むそうです。



トルコも世界有数の喫茶愛好国です。

ロシア風のサモワールで沸かして、砂糖をたっぷり入れてチャイ(紅茶)を飲みます。



牧之原大茶園
我が国有数の大茶園を見てみましょう。

徳川幕府瓦解後、多くの幕臣が失業し途方にくれていました。

中條景昭らが幕臣の勝海舟に相談します。「島田の荒れ地を開墾して、お茶を植えたい」と。

こうして勝海舟から見事資金の援助を引き出せました。

また当時、大井川に橋が架かることになり、川越人足たちも失業していました。

で、川越人足たちも茶畑の開墾に加わることとなりました。

牧之原大茶畑は徳川幕府の遺産のようなものなのですね。

これは昭和中期の製茶機械です。

防霜ファンです。空気をかき混ぜ、寒い空気が下に溜まらないようにします。


小堀遠州の庭園
小堀遠州は江戸初期の茶人、建築家として知られます。

この庭園は、遠州が手がけた後水尾院の仙洞御所を再現したものです。







小堀遠州ゆかりの茶室「縦目楼」でお茶も頂けるそうです。







ミュージアム&カフェです。

手揉み体験も出来る。


抹茶アイス。

最も味の濃い抹茶No.7を所望しました。濃厚やった。

蓬莱橋(ほうらいばし)
大井川に架かる蓬莱橋に行ってみました。

島田側と反対側から渡ることにします。現在吉祥天女とある側にいます。


蓬莱橋は全長897.4メートル。世界最長の木道歩道橋らしい。


江戸時代、大井川には橋が架けられませんでした。

渡し舟さえ許されず、川越人足を使うしかありませんでした。

しかし幕府瓦解後に架橋が許され、1879年に蓬莱橋が誕生したのです。

箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川


勝海舟の像です。牧之原開拓に尽力しました。


渡る前にここで百円払います。

川越人足の様子です。


JR島田駅
JRの島田駅です。

駅前には鎌倉時代の禅僧・栄西の像です。

栄西は本格的なお茶文化を日本に紹介したといわれます。








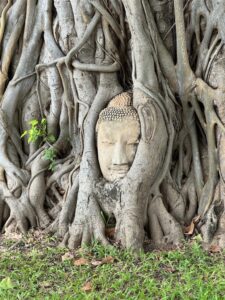




コメント